タクシードライバーに必要な英語のスキル【英会話フレーズ75選】
外国人観光客の増加に伴い、タクシー業界においても外国人のお客様を乗せる機会は増えてきました。タクシードライバーとして少しでも英語を話せたほうが、外国人の乗客とのコミュニケーションが円滑に進むでしょう。ここでは、シーン別で使える簡単な英語フレーズについて紹介していきます。 関連記事 タクシー運転手が知っておくべき接客やビジネスマナー タクシー関連の英語表現
そもそも「タクシー」は「taxi」と表現します。発音は「タクスィ」で「タ」にアクセントを置いて強調し、語尾は「シー」ではなく「スィ」と発音するとよりネイティブに近い発音になります。国によっては「cab」「taxicab」などと表現される場合もあります。また、「タクシーを呼ぶ」は「call a taxi」、「タクシーをつかまえる」は「pick up a taxi」、「タクシー乗り場」は「a taxi stand」などと表現されます。 お客様との会話で使える基本的な英語フレーズ
英語をすぐに話すことは難しいかもしれません。ただし、仕事で使う可能性のあるフレーズだけでもあらかじめ覚えておけばスムーズな接客ができるでしょう。以下では、「乗車時」、「走行時」、「会計時」に分けて基本的な英語フレーズを紹介していきます。また、「車内で使える雑談」も紹介しますので、英語での会話に慣れてきたら使ってみましょう。 乗車時に使える英語について
お客様が乗車してきたら、まずは「Hello!」と気持ちよく迎えましょう。その後、以下のフレーズを使ってください。 “Please get in.” (どうぞご乗車ください。)
“Let me close the door.” (ドアを閉めます。) この際には会話以外でも気をつけたい点があります。それはタクシーの自動開閉式ドアです。外国人観光客の多くは自動で開閉するドアに慣れていません。お客様の足や荷物を挟まないように注意しましょう。お客様が乗車したら、行き先を聞きます。 “Where are you going?” (どちらまで行かれますか?)
“What is your destination?” (行き先はどちらですか?)
“Do you have the address?” (行き先の住所はわかりますか?) 上記のフレーズを使ってください。また、お客様に目的地までの距離や時間などを聞かれることもあるでしょう。例えば、“How far is Kaminarimon from here?”(ここから雷門まではどのくらいですか?)と聞かれた場合には以下のように答えます。 “It takes about 30 minutes if there is no traffic.” (渋滞がなければ約30分で到着します。) このように的確に答えられるようにしておくとよいでしょう。 関連記事 タクシードライバーってカーナビを使ってもいい?使わないほうがいい? 走行時に使える英語について
お客様から行き先を聞いたら、いよいよ出発です。出発時に使える英語フレーズについては以下を参考にしてください。 “Please fasten your seatbelt.” (シートベルトをお締めください。)
“I need you to buckle up, it’s the law.” (シートベルトの着用は法律で義務づけられています。)
“Thank you for your cooperation.” (ご協力ありがとうございます。) また、交通渋滞を避けられないケースも多々あると思います。もし、走行時に渋滞に遭遇してしまった場合には、お客様に一声かけることを心がけましょう。 “I am sorry but we are stuck in traffic.” (ご迷惑おかけしますが渋滞にはまっています。)
“It should take 15 minutes or so to get out of the traffic.” (渋滞を抜けるのに15分くらいかかりそうです。)
“Do you want to take a detour to avoid the traffic jam?” (渋滞を避けるために迂回しますか?)
“Would you like to take a toll road?” (有料道路を利用しますか?) 会計時に使える英語について
目的地に到着したら最後は会計です。スムーズな会計をして最後まで気持ちのよいサービスを心がけてください。基本的な英語フレーズは以下のとおりです。 “It's 2,400 yen.”(2,400円です。)
“It is 2,400 yen including the highway fee.” (高速道路の料金を含めて2,400円です。)
“We accept credit cards.” (クレジットカードのご利用も可能です。)
“Would you like the receipt?” (レシートはご利用ですか?)
“I don’t have a chipping custom system.” (チップはいりません。)
“Thank you for your ride.” (ご乗車頂きありがとうございます。) 雑談に使える英語について
基本的な会話のやり取りに慣れてきたら、次は雑談をしてみましょう。雑談に使える英語は以下のとおりです。 “When did you arrive Japan?” (日本にはいつ着いたのですか?)
“Is it sightseeing? Or business?” (観光ですか?それとも仕事ですか?)
“Until when are you staying?” (日本にはいつまで滞在するのですか?)
“Which country are you from?” (どちらの国から来られたのですか?)
“Enjoy your stay. Welcome to Japan!” (日本滞在を楽しんでくださいね!) 実際の会話例は以下の通りです。 運転手 「Which country are you from?」(どちらの国から来られたのですか?)
乗客 「I came from America. 」(アメリカから来ました。)
運転手 「Is it sightseeing? Or business?」(観光ですか?仕事ですか?)
乗客 「For sightseeing.」(観光です。)
運転手 「Enjoy your stay. Welcome to Japan!」(日本滞在を楽しんでくださいね!) お客様がよく使う英語のフレーズ
ここまではお客様に対してタクシードライバーが使う英語のフレーズをお伝えしました。ここからは、お客様が使う英語のフレーズをご紹介します。どういったことが、どういう表現で言われるのか知っておくのは重要なことです。それを知っておくことによって、お客様が言った内容を聞き取りやすくなりますし、理解もしやすくなります。円滑にコミュニケーションを取るためにも、お客様がよく使う英語のフレーズを学んでいきましょう。こちらに関しても「乗車時」、「走行時」、「会計時」に分けて基本的な英語のフレーズをご紹介します。 乗車時によく使われる英語
まずは、お客様をタクシーに乗せる場面。以下のような質問をよく受けます。 “May I get in?” (乗車してもよいですか?)
“Could you put it in the trunk?” (トランクに積んでいただけますか?)
“Can you put the baggage in the trunk?“ (トランクに荷物を入れてもらえますか?)
“Open the trunk, please.” (トランクを開けてください。) アメリカやイギリスでは行き先を伝え、タクシードライバーと合意したら交渉成立となり、乗車する流れとなっています。そのため、最初に乗車してもよいか聞かれることがあるでしょう。それに対しては“Sure.” (もちろんです。)といったように答えてください。 また、荷物に関してですが、“baggage”はアメリカ英語となり、イギリス英語では”luggage”と表現します。発音的にはそこまで変わらないので迷うことは少ないかもしれませんが、タクシードライバーがよく聞く単語となりますから覚えておきましょう。乗車後には、話題は行き先へと移ります。 “Can you take me to the Narita Airport, please?” (成田空港までお願いします。)
“Can you go to at the Tokyo Skytree?” (東京スカイツリーまでお願いします。)
“I would like to go to the Tokyo station.” (東京駅まで行きたいです。)
“I want to go to the Tokyo station.” (東京駅まで行きたいです。)
“I’m going to the Tokyo station.” (東京駅まで行きます。)
“Take me to this address, please.” (この場所まで連れて行ってください。) お願いをするに当たっては「~してくれますか?」という意味になる“Can you ~ ?”や、それをさらに丁寧にした“Could you ~ ?”という表現を使うのが一般的です。行き先を伝えるのに関してはお客様が行きたい先が分かればよいことから、「~したい」という意味になる“I want to go to ~.”や、その丁寧表現に当たる“I would like to go to ~.”を使うこともありますし、“I’m going to ~.”で「~に行きます。」と言われることもあります。また、地図を見せてきて、ここまで連れて行ってほしいと伝えられることもあります。 途中で寄りたい場所があるときなど、行き先が複数ある場合には以下の表現を使います。 “Can you stop by restaurant before you go to Akihabara station?” (秋葉原駅へ行く前にレストランに寄ってもらえますか?)
“Could you wait for me here, please?” (ここで待っていてもらえますか?)
“Can you wait for a few minutes in here?” (少しだけ待っていただけますか?) 目的地までの所要時間を質問されることがあります。 “How long will it take to get there?” (そこまで行くのにどのくらいの時間がかかりますか?)
“How long does it take to the airport?” (空港まではどれくらいかかりますか?) 時間についての質問に答えるときには“It takes about 30 minutes.” (30分くらいかかります。)といった表現を使ってください。
続いては料金に関しての質問です。 “How much will it cost?” (いくらくらいかかりますか?)
“About how much?” (いくらくらいかかりますか?)
“Can you take me there for 5,000 yen?” (5,000円でそこまで行っていただくことはできますか?)
“Do you offer flat rates?” (固定料金はありますか?) 観光タクシーやハイヤーの場合には固定料金がありますから、固定料金の有無について聞かれることもあります。 走行時によく使われる英語
続いてはタクシーを走らせているときにお客様の使う英語のフレーズについて見ていきましょう。お客様が土地に詳しかったりこだわりがあったりする場合には走る道の誘導を受けることもあります。 “Can you make a right turn?” (右に曲がってください。)
“Can you make a left at the next light?” (次の信号で左に曲がってください。)
“Keep on going straight.” (真っすぐに行ってください。)
“Follow the road.” (道なりに進んでください。)
“Stop in front of the Kyoto station.” (京都駅の前で停まってください。)
“Go in the driveway.” (ドライブウェイに入ってください。) ドライブウェイとは、車道から家屋やビルの入り口前に通じる私設道のことを言います。分からなければ“Can you make a right turn?”などと言い換えてくれるとは思いますが、その間にもタクシーは進んでいます。ギリギリになってからお客様からの指示を理解し、急に曲がるのは危険です。普段とは違う、外国語での会話に緊張するかもしれませんが、安全を最優先させていきましょう。 お客様によっては急いでいることもあります。そんなときに使われる表現も確認しておきます。 “Take the shortest way, please.” (一番近い道で行ってください。)
“Can you hurry up?” (急いでもらえますか?)
“Can you get there by 8:00 p.m.?” (午後8時までに着けますか?)
“Can you go faster?” (もう少し速く走れますか?)
“Are we almost there?” (そろそろ着きますか?)
“How much longer?” (あと何分くらいですか?)
“Here's fine.” (ここでけっこうです。) 急いでいるときに渋滞などに巻き込まれたときには“Here's fine.”といって降車する方もいます。また、目的地近くになって、降車場所を指定するときにもこのフレーズが使われます。 会計時によく使われる英語
最後は降車の際に使われる英語のフレーズです。支払いで使われる英語のフレーズも覚えておいてください。 “Can I use credit cards?” (クレジットカードは使えますか?)
“May I have a receipt, please?” (領収書をもらえますか?)
“Can I have the change please?” (お釣りをください。)
“Keep the change.” (お釣りは取っておいてください。) 外国人観光客が増えている昨今、タクシードライバーにも英語のスキルが求められています。ここに紹介した75の英語フレーズの中から、まずは2つ3つだけでも覚え、接客するときに実際に使ってみてください。少しずつ英語が話せるようになっていき、タクシードライバーとしての価値を高めていきましょう。 新着タクシー求人を見る タクシー運転手の英語学習におすすめの書籍
タクシー運転手の英語学習におすすめの本を4冊ご紹介します。 ・30歳高卒タクシードライバーがゼロから英語をマスターした方法
著者である中山哲成さんがごく普通のタクシードライバーから、4年間で英語をペラペラと自由に話せるようになった勉強方法が公開されています。 ・海外からのお客様を英語で案内・応対するための表現集
タイトルの通り、海外から来日した方々が日本滞在中に観光・ショッピング・食事・宿泊・移動などの様々な場面で気持ちよく過ごせるように、英語で案内・接客・応対できる表現、および日本の文化や観光地なども紹介できる表現を収録しています。この一冊をマスターすることで英語でスムーズに会話をすることが可能となるでしょう。 ・外国人送迎ドライバー向け接遇マナーの基本と接客英語
元国際線キャビンアテンダントが4年にわたりドライバーに接客英会話の研修を実施してきた経験を活かして書き上げられたドライバー向けのテキストです。マナーの必要性から接客英語の基本フレーズ、覚えておきたい英単語も収録されており、外国人に向けた「日本のおもてなし」を表現するための接客英語とマナーを学ぶことができます。 ・キクタン接客英会話【交通編】
耳を使った学習で使える英語をモノにできるキクタンシリーズの【交通編】です。「電車」「タクシー」「バス」「レンタカー」などのジャンル分けて、全61シーン207フレーズを取り上げています。「タクシー」ジャンルを重点的に言えるようにすることで十分な英語力が見につけられるでしょう。 外国人旅行客の増加を受けて各社でも能力開発!今、タクシードライバーに求められるスキルは?
近年、日本政府より観光立国の推進を受けて日本への外国人旅行客が増加傾向にあります。それを受けて、羽田空港国際線の発着枠を増加するなど、外国人によるタクシー利用率が上がってきています。そこで、タクシー業界ではタクシードライバーに外国人の接遇面をさらに強化するため、さまざまな取り組みをしています。今回は、現在のタクシードライバーが力を入れている外国人の待遇面をご紹介します。 東京のタクシードライバーの取組み『外国人旅客接遇研修』とは
東京は、日本でも多くの観光地が集まる場所として多くの外国人旅行客が集まる地として注目されています。そこで、東京で働くタクシードライバーが研修時に必ず訪れる江東区にある「東京タクシーセンター」では、外国人旅行客の接遇面を強化するために『外国人旅客接遇研修』という研修を実施しています。研修内容は、レベルに応じて色々と違いますが、ロールプレイング実習を取り入れた研修が主になっており、外国人の習慣を学び、普段タクシードライバーが営業で使う英語や緊急時の対応(英会話)などを習得して接遇向上を目的に行われています。レベルは、初級~上級まであり、研修内容をICレコーダーなどで録音も可能なので、タクシードライバーの多くは受講後、自身で発音などのトレーニングをしています。研修費用は、1受講2,700円となっており、申込みは直接「東京タクシーセンター」へ電話連絡して予約します。また、各種学習教材なども用意されているので、それを購入して勉強をするタクシードライバーも多いようです! 関連記事 東京のタクシードライバー(タクシー運転手)での勤務は稼げる?稼げない?地方との月収の違いはどのくらい? 英語講習会を取り入れているタクシー会社が増加
外国人旅行客の増加を受け、東京観光事業に力を入れているタクシー会社のほとんどが英語講習会などの語学研修会を開き、外国人向けの接遇に強化を図っています。タクシー会社の中には、英語以外にも韓国語や中国語、フランス語もできるタクシードライバーも在籍しており、これを見ても分かるように今やタクシードライバーも語学力が求められる職業になったといえるでしょう。タクシー会社によっては、語学レベルごとに配車先を振り分ける活動をしているところもあるようです。このような仕組みのタクシー会社もあるので、タクシードライバーは、一人でも多くのお客様獲得に向けて積極的に研修会に参加しています。 日本最大手『日本交通』の外国人旅行客向けに行っている取り組み
東京観光事業に最も力を入れているのが、日本最大手『日本交通』と言っても過言ではないでしょう。日本交通では日本での国際化を受け、いち早くさまざまな研修を取り入れています。たとえば、1ヶ月のロンドン留学研修や独自のテキストを用いて毎月2回の英語講習会開催など、語学面の強化に力を入れています。また、日本交通では研修だけでなく、東京観光を盛り上げるため、株式会社ぐるなびと提携し、旅情報誌「ぐるたび」内に特設ページを設置するなど、外国人観光客問わず観光を目的とする全ての人にタクシー利用に繋がる活動を積極的に実施しています。ちなみに「ぐるたび」とは、旅先のグルメ体験や旅の楽しい情報を地元住民や地元密着のライターによって発信するサイトで、日本交通の特設ページには東京観光ドライバーがタクシードライバーならではの観光スポットを紹介する情報サイトです。 タクシードライバーのこれから
今後日本国内にはますます外国人旅行客が増えると考えられます。これからタクシードライバーを目指す方も、既にタクシードライバーの方も、中長期視点ではさまざまな乗客のニーズに合わせた接客、接遇が求められてくると思われます。既に外国人旅行客からは日本のタクシーは接遇がとても素晴らしいと評価されていますが、スキルアップしていくことでタクシー利用者は今後さらに増えていくことが期待できます。今からでも遅くありません!少しずつ簡単な英会話から勉強してみてはいかがでしょうか?! ドライバーズワークの公式ウェブサイトであるタクノート -タクnote- では、タクシーに関連する様々なコラムを豊富に取り揃え、タクシードライバーとしての知識やスキル、業界の最新トレンドなど貴重な情報を提供しています。ぜひタクノートを利用して、あなたのタクシードライバーとしてのスキルや知識を向上させましょう! 関連記事 プロドライバーになるための定義・条件とは 新着タクシー求人を見る




















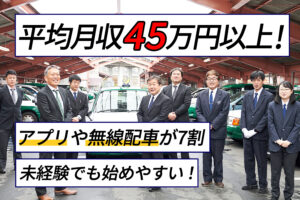





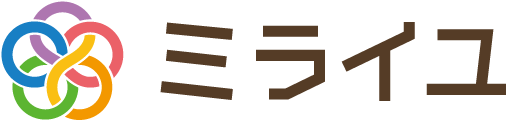














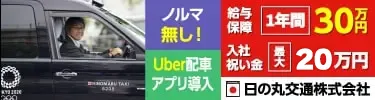




 無料会員登録
無料会員登録 