タクシー運転手の年齢制限は?
タクシー業界への転職を考えている人の中には、年齢制限について疑問を抱いている方もいるでしょう。こちらの記事ではタクシー会社で働ける年齢についてご紹介します。
法的には年齢制限が設けられていない
タクシー業界においては、運輸や労働に関する法令には年齢制限が設けられていないことが一般的です(個人タクシー業を除く)。タクシー運転手の勤務は長時間労働や不規則なシフトが多い一方、年齢制限がないため、中高年の方々が他の職種から転職するケースが多く見られます。実際、タクシー運転手の平均年齢は58歳を超えており、他の産業全体の平均年齢(約42歳)よりもかなり高くなっています。そのため、70歳や80歳になっても、適切な運転スキルと接客能力を保持している限り、タクシー運転手として活躍することは可能です。
一方でタクシードライバーは若い世代にも向いている!
一般的な職業において、20代は経験が浅く、高度な仕事に進むための基礎を築く時期であり、高収入を得るのは難しいことがあります。しかし、タクシー運転手の場合、ほとんどの会社が歩合制を採用しているため、経験や年齢に関係なく、高い収入を得るチャンスがあります。つまり、自分の努力が売上に直結し、それが給料に反映される仕組みです。
もし売上が思うように伸びなかった場合でも、会社員としての固定給与があるため、最低限の収入は確保できる点が安心材料です。このため、20代や30代などの若い世代が特に積極的に働き、成果を上げて高収入を得ることが期待できます。また、20代からタクシー運転を始めた人の中には、30代になって個人タクシー業者として独立し、成功している人もいます。
タクシー運転手の平均年齢
前述したように、若い世代もタクシー運転手として活躍できる可能性がありますが、実際のタクシー運転手の平均年齢は何歳でしょうか?都道府県別に見ると、山梨県が最も高く、平均年齢は74.9歳で、最も若い場所でも東京都で51.8歳となっています。全国平均では、タクシー運転手の平均年齢は58.3歳であり、50代から60代の人々が多く働いています。つまり、若い世代が増加していると感じられるかもしれませんが、全国的には依然として高齢の運転手が多いのが現状です。
タクシー運転手の勤続年数
タクシードライバーの平均勤続年数は、短い場合でも5.7年、長い場合でも15年程度です。このデータからも、平均年齢が高いことと合わせて、多くの人が40代や50代からタクシードライバーとしてのキャリアをスタートさせていることが分かります。通常、一般の企業では60歳や65歳で定年退職となることが一般的ですが、タクシー会社では70歳以上のドライバーも多く見られます。さらに、多くのタクシー会社が第二種免許取得に関して全額負担しているため、一般企業での経験を積んだ後にタクシー業界に転職する人が増えている一因といえるでしょう。
まとめ
タクシー業界は、年齢に関する法的制限がないため、幅広い年齢層の人々にとってキャリアチャンスがある分野といえます。しかし、現実には平均年齢が比較的高い傾向があります。都道府県ごとに異なりますが、全国平均でタクシードライバーの平均年齢は約58歳です。このデータから分かるように、タクシー運転手としてのキャリアは、多くの場合、40代や50代からスタートする人が多いです。平均勤続年数も、短い場合で5.7年、長い場合でも15年ほどです。
一般企業では60歳や65歳が定年退職の年齢とされていますが、タクシー業界では70歳以上の運転手も多く見られます。また、第二種免許取得に関しては、多くのタクシー会社が費用を全額負担しており、これが一般企業からタクシー業界へ転職する人が増える要因となっています。
要するに、タクシー業界は年齢にとらわれず、幅広い世代の人々にとってキャリアの選択肢がある職業であり、経験や努力によって高収入を得るチャンスが広がっています。
タクシードライバーへの転職で失敗しないために
タクシードライバーの転職で失敗しないためには、ぜひドライバーズワークにご登録・ご相談ください。タクシードライバーは中高年になってからも末永く続けていける数少ない仕事のひとつであり、未経験からでも活躍のチャンスがたくさんある職種ですが、タクシー会社によって特徴はさまざま。どんな基準で選べば良いのか?未経験だが大丈夫か?などの心配も出てくることと思います。専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの担当に付き、転職にまつわるあなたのお悩みにお答えするだけでなく、転職をするべきなのかどうか、転職をする場合にどういった基準で会社選びをすれば良いか、などを一緒に考え丁寧にお伝えします。まだ転職するかどうかを迷っている段階の方も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
関連記事
キャリアの人気記事
よく読まれている記事
- 知識
タクシー運転手になるにはどんな資格が必要?ドライバーの条件とは
【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...
- 知識
【地理試験の疑問】過去問・テキストの入手方法や受験場所・時期!タクシードライバーになるには必要?
【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...
- 知識
タクシードライバーの勤務体系・勤務時間を勤務スタイルの例で徹底解説!
みなさんが普段見かけるタクシーは朝も夕方も夜中も走っており、いつ休んでいるのかと思うほどどの時間帯で見かける...
- 知識
タクシーの営業区域や区域外営業などエリアについて
タクシーは場所を選ばず自由に営業をして良いという訳ではありません。「営業区域」と呼ばれる、タクシー会社ごとに...
- 知識
タクシーに自転車は乗せられる?自転車を積む方法と運ぶ際の注意点
趣味で自転車に良く乗る方や、自転車で通学・通勤をしている方にとって、途中で自転車に乗れなくなってしまった場合...
- 知識
タクシー車内で飲食しても良い?守るべきマナーも紹介
タクシーにまつわるマナーの1つに、タクシーの車内で飲食することの是非があります。今回はタクシー車内での飲食に...
タクシードライバーについて知る
他のコラム内カテゴリもチェック!
キャリア
タクシードライバーとして仕事をするにあたってのお役立ち情報をご紹介します。タクシーエンタメ
タクシー業界に関連する面白いエピソードや、エンターテイメント情報をご紹介します!タクシーニュース
タクシー業界や運輸業界に関する新着ニュースをご紹介!タクシーの種類
利用シーンによって様々あるタクシーのサービス形態をご紹介します!テクニック
タクシードライバー(運転手)としてのテクニックにまつわる情報をお届け!無線グループ
大手グループから地域密着のグループまで!無線グループの特徴をご紹介します。Q&A
タクシー業界やタクシードライバーに関するよくある質問にお答えします!知識
タクシー業界にまつわるトリビアや豆知識情報をご紹介します!





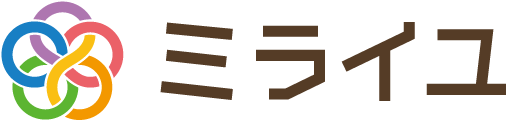









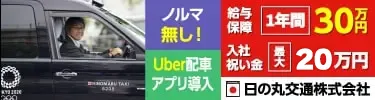




 無料会員登録
無料会員登録 