コロナ禍におけるタクシー業界の運転手の現状と対策とは?

新型コロナウイルスでは、仕事にも私生活にも様々な影響がありました。タクシー業界も例外ではなく、コロナ以前とは状況がまったく異なっています。そこで、今回はタクシー業界の現状を確認し、タクシー運転手が行っているコロナウイルスへの対策について見ていきましょう。
タクシー業界の現状は?
新型コロナウイルスが猛威を振るい、世界に大きな影響を与えました。国内でも緊急事態宣言がなされ、国全体で外出自粛を推し進めてきました。コロナウイルスの蔓延が世間的に言われてきてから緊急事態宣言を受けたタイミングでは、普段なら賑わう週末の大都市、渋谷や新宿からも人影がなくなりました。タクシー運転手からすると、「お客様どころか人がいない」という状況です。そのため、流し(街中を走りながらお客様を探すこと)をしてもお客様が見つからないことしばしばです。
この度緊急事態宣言が解除され、オフィスへの勤務が始まるなど、外出する方が徐々に増え始めています。これまでの人の量に比べれば、その数はまだ多くはありませんが、今後飲食店が夜間の営業を再開したときには以前と同じような活気が戻ってくるでしょう。
また、タクシー事業者には特例として有償貨物運送の業務をすることが認められています。タクシーはお客様の目的地までの移動をサポートする旅客として事業を行っており、有償貨物運送の業務は行えません。有償貨物運送は、簡単に言うとデリバリーサービスのようなものです。つまり、この特例によって、お店が提供する料理を、お客様の自宅まで運ぶサービスを提供できるということです。コロナの感染リスクを防ぐために外出したくないお客様と、店舗での営業はできないが購入してもらえないと経営が成り立たない飲食店をつなぐ、サービスを展開しています。
この他、お客様の代わりに買い物を行う「おつかいタクシー(お買い物代行タクシー)」というサービスも提供しています。
関連記事 話題のおつかいタクシー(お買い物代行タクシー)とは?
関連記事 タクシー配車アプリ「JapanTaxi」について
タクシー業界の対応は?
コロナウイルスの拡大を防ぐため、タクシー業界でも様々な取り組みが行われています。タクシー運転手自身がコロナに感染しないように注意するとともに、お客様間で感染させないように対応しています。
厚生労働省の呼び掛けている「密閉空間・密集場所・密接場面」、いわゆる「3つの蜜」を避けることはもちろん、タクシー運転手がマスクをする・私語を慎む・車内の消毒をするなどしています。どんなときにどんなことを行っているのか、具体的にタクシー運転手の仕事に沿って見ていきましょう。
通勤時
タクシー運転手という職業から考えると、電車に乗るイメージが湧かないかもしれませんが、事務所までの通勤に電車を利用する方もいます。そこで、通勤時の混雑した状況下での乗車を避けるために、変形労働時間制や週休3日制などを導入しています。
また、発熱やせきなどでコロナの症状が疑われる方や、感染者と濃厚接触が疑われる方には自宅待機が命じられています。
乗務開始前
出勤してから乗務開始前までの間には、検温を行っています。朝と夕方で1日に2回検温します。検温時に発熱がある場合には乗務ができません。また、普段乗務の前にはアルコールが入っていないか確かめるためにアルコール検知器を使うのですが、この検知器に関してもこまめに除菌したり、検知器の数を増やしたりして、タクシー運転手間での感染リスクを避ける対策をしています。
乗務中
タクシー運転手はお客様を乗せるときにも、マスクを着用し、私語はなるべく慎むようにしています。そして、お客様には基本的に後部座席を利用してもらい、助手席には乗らないように呼び掛けています。
お客様が降車した後は、窓やドアを開けてよく換気し、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなどを使って車内を消毒します。
タクシー会社によってはコロナ対策として、タクシーの運転席と後部座席の間に、透明のビニールカーテンやアクリル板などで仕切りを作っています。仕切りとなっている場所の後部座席側、それから手すりやタブレットなど、お客様がよく触る場所を中心に拭きあげていきます。消毒したりゴミを拾ったりと、車内を掃除する際にはマスクや手袋を着用して行い、作業後には手洗いを徹底しています。
乗務終了後
タクシー会社では「1車2人制」や「2車3人制」などと呼ばれるように1台のタクシーを複数人で使いながら営業を行いますので、自分が乗務を終えた後には、次のタクシー運転手が乗務することになります。そうしたこともあり、乗務終了後には、お客様を降車させた後と同じように、換気・消毒を行います。
関連記事 タクシードライバーの点呼から終業までの1日の流れ
関連記事 「1車2人制」や「2車3人制」とは?1台のタクシーを2人の乗務員で使う具体例を詳しく解説!
コロナ禍におけるタクシーの役割とは?
通勤・通学の手段には様々ありますが、その中でも公共交通機関を利用する方も少なくないでしょう。コロナウイルスでの騒動が落ち着き、コロナ以前と同様に経済活動が始まると、電車やバスなどの公共交通機関には人が多くなり、満員電車になることも想定されます。もし本当にコロナの前と同様に満員電車となってしまった場合には、感染リスクが高まるでしょう。
そこで、タクシーが役立ちます。先にもお伝えしたように、タクシー業界でも様々なコロナ対策を行っております。どちらにリスクがあるかは人によって感じ方が異なりますが、満員電車に乗るのはリスクが高いと言えるでしょう。通勤・帰宅の手段として満員になりやすい電車やバスなどの公共交通機関の利用を避け、タクシーを利用する手段も検討してみる必要がありそうです。
今回はコロナ禍におけるタクシー業界の現状と対策についてお伝えしました。タクシー業界でもマスクの着用や、車内の消毒など、コロナに対しての取り組みを行っております。新型コロナウイルスによって退職を余儀なくされ、仕事に迷っている方もいるでしょう。もしそうでしたら、タクシー運転手として働くこと検討してみてはいかがでしょうか。
タクシー運転手は40代、50代以上などの中高年の方でも未経験から活躍できるチャンスがありますので、ご転職をお考えの際はぜひタクシー業界も検討してみてください。これからタクシーの仕事をお探しならドライバーズワークでタクシー運転手の求人を検索していきましょう。タクシー業界に精通したキャリアアドバイザーが相談に乗ることも可能!お悩みの方はぜひ活用してみてください。
タクシードライバーへの転職で失敗しないために
タクシードライバー(運転手・乗務員)の求人、転職にご興味がおありなら、ぜひドライバーズワークにご登録・ご相談ください!登録はかんたん1分無料!「実際いまはどれくらい稼げるの?」「この会社の職場環境ってどうなの?」など求人の裏側の情報もお伝えすることができます。中には非公開求人も!ご登録後は、専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの担当に付き、転職にまつわるあなたのお悩みにお答えするだけでなく、転職をするべきなのかどうか、転職をする場合にどういった基準で会社選びをすれば良いか、などを一緒に考え丁寧にお伝えします。まだ転職するかどうかを迷っている段階の方も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
関連記事
タクシーニュースの人気記事
よく読まれている記事
- 知識
タクシー運転手になるにはどんな資格が必要?ドライバーの条件とは
【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...
- 知識
【地理試験の疑問】過去問・テキストの入手方法や受験場所・時期!タクシードライバーになるには必要?
【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...
- 知識
タクシードライバーの勤務体系・勤務時間を勤務スタイルの例で徹底解説!
みなさんが普段見かけるタクシーは朝も夕方も夜中も走っており、いつ休んでいるのかと思うほどどの時間帯で見かける...
- 知識
タクシーの営業区域や区域外営業などエリアについて
タクシーは場所を選ばず自由に営業をして良いという訳ではありません。「営業区域」と呼ばれる、タクシー会社ごとに...
- 知識
タクシーに自転車は乗せられる?自転車を積む方法と運ぶ際の注意点
趣味で自転車に良く乗る方や、自転車で通学・通勤をしている方にとって、途中で自転車に乗れなくなってしまった場合...
- 知識
タクシー車内で飲食しても良い?守るべきマナーも紹介
タクシーにまつわるマナーの1つに、タクシーの車内で飲食することの是非があります。今回はタクシー車内での飲食に...
タクシードライバーについて知る
他のコラム内カテゴリもチェック!
キャリア
タクシードライバーとして仕事をするにあたってのお役立ち情報をご紹介します。タクシーエンタメ
タクシー業界に関連する面白いエピソードや、エンターテイメント情報をご紹介します!タクシーニュース
タクシー業界や運輸業界に関する新着ニュースをご紹介!タクシーの種類
利用シーンによって様々あるタクシーのサービス形態をご紹介します!テクニック
タクシードライバー(運転手)としてのテクニックにまつわる情報をお届け!無線グループ
大手グループから地域密着のグループまで!無線グループの特徴をご紹介します。Q&A
タクシー業界やタクシードライバーに関するよくある質問にお答えします!知識
タクシー業界にまつわるトリビアや豆知識情報をご紹介します!





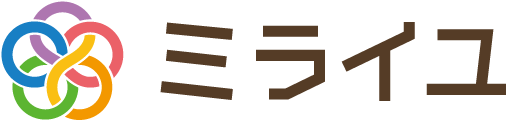



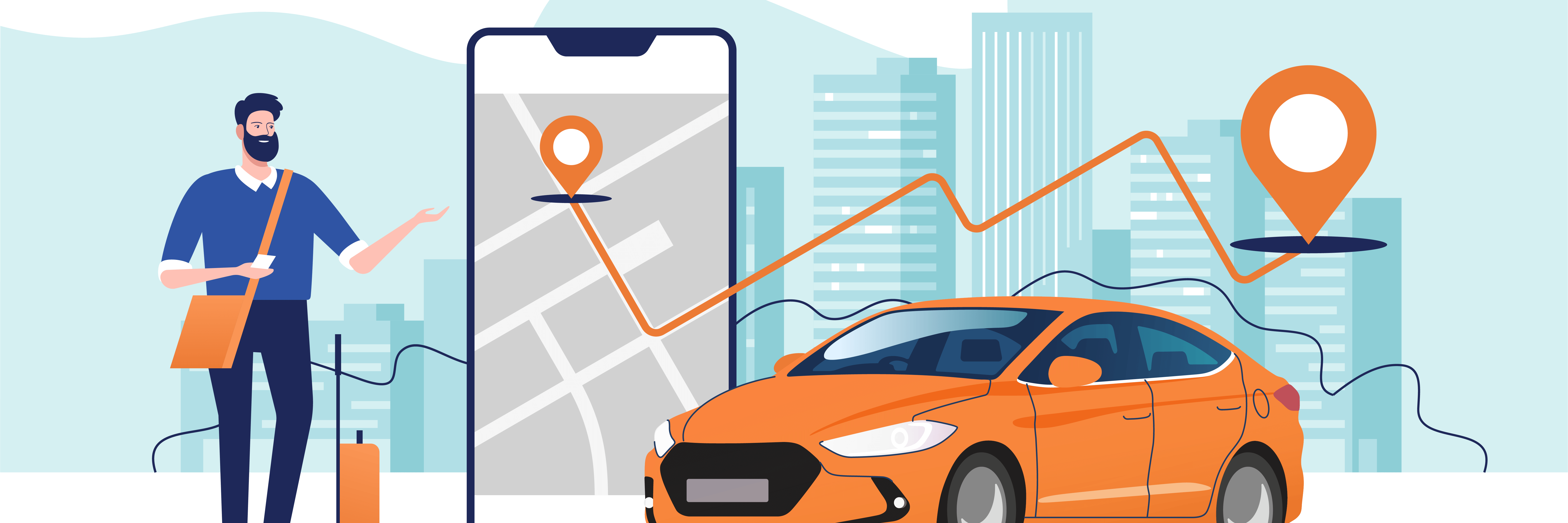


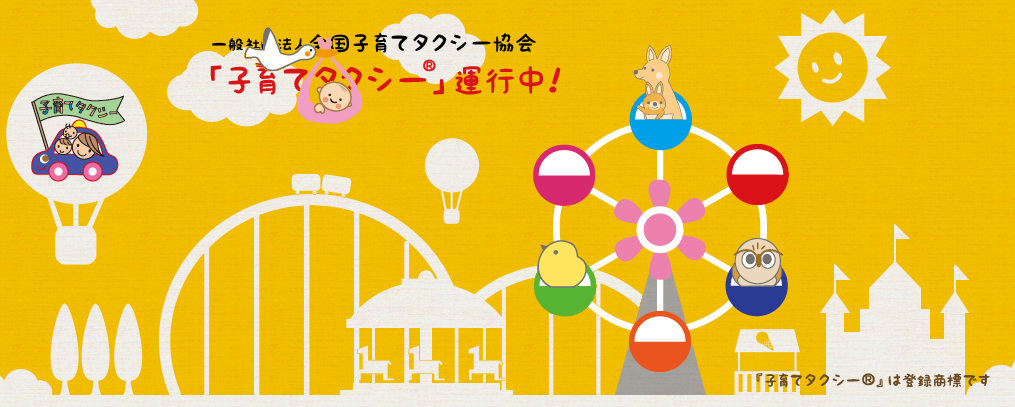



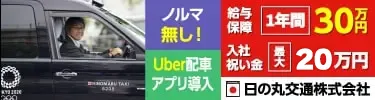




 無料会員登録
無料会員登録 