個人タクシーの運転手になる条件とは?法人タクシーとの違いとは

タクシー運転手には大きく分けて、個人タクシーと法人タクシーの2種類があります。法人タクシーは、タクシー会社が所持するタクシーのこと、もしくは会社に所属して乗務する運転手のことを指します。その一方で個人タクシーがあります。個人タクシーは、法人タクシーとは何が違うのでしょうか?また、個人タクシー運転手になるにはどうしたら良いのでしょうか?今回は個人タクシーに焦点を当てて見ていきましょう。
個人タクシーとは
個人タクシーとは、会社に所属せずに個人事業主として乗務をするタクシー、またはその運転手のことです。企業に所属しないため、乗務の自由度が上がり、タクシー車内の雰囲気も働き方も自由に選べる魅力があります。
個人タクシーの運転手になるには、まず法人タクシーの運転手として働く必要があります。法人タクシーの運転手になるには、タクシー会社の採用面接を受けて合格する必要があります。その後に研修を受けて資格を取れば、法人タクシー運転手としてお客様を乗せることができるようになります。
個人タクシーの運転手(事業者)になるための条件
10年のタクシー乗務経験が必要になる
法人でタクシー乗務をするためには、二種免許が必要になり、東京・神奈川・大阪の一部の都心エリアで働くには、その土地について豊富な知識が必要となることもあり、地理試験の合格が必要となります。タクシー会社に採用された後、約1ヶ月間の研修を受けて資格を取得すれば、タクシー運転手として乗務を始めることができます。個人タクシー運転手になるには、タクシー会社に所属し、タクシーやハイヤーの運転手として10年働く必要があります。
個人タクシーの運転手に憧れるのなら、いち早く法人タクシーの運転手として働き始めることをおすすめします。
でも、「タクシー会社の選び方が分からない…」、あるいは「おすすめのタクシー会社を知りたい…」と感じている方のために、ドライバーズワークでは業界に精通したキャリアアドバイザーが無料でご質問に対応しております。少しでもタクシー運転手にご興味のある方は、まずは話だけでも聞いてみると良いでしょう。
条件は年齢によって変わる
個人タクシーの運転手になるための条件は、年齢によって違いがあります。以下の表で詳細を確認してみてください。
| 個人タクシー事業者になる条件 | ||
|---|---|---|
| 年齢 | 条件 | |
| 35歳未満 |
| |
| 35歳以上 40歳未満 |
| |
| 40歳以上 65歳未満 |
| |
つまり、個人タクシー運転手として働きたいと考えている方は、55歳までにタクシー業界で働き始める必要があります。法人タクシーで経験とスキルを得ながらも、上記の条件を守り、個人タクシーの運転手になる準備をしていきましょう。個人タクシーになるための条件は年齢が上がるにつれて緩和されていきます。例えば、年齢が35歳以下の場合には申請日以前10年間、無事故無違反である必要がありますが、35歳以上は3年間以上の無事故無違反が条件となっているのです。
ただ、年齢が何歳であろうとドライバー業を10年以上継続していることが条件なので、どちらにしても個人タクシーの運転手になる道は簡単とは言えません。さらに、運転経歴の計算方法は「在籍証明書」、「乗務員台帳の写し」、「タクシーセンターの発行する運転者登録原簿」や「社会保険の加入状況を証明するもの」で確認していきます。例えば、在籍証明書で入社が確認できても、社会保険に未加入の場合はその期間をカウントされませんので、ご注意ください。
営業区域に住む必要がある
個人タクシーになれば自由になると考えている方もいるでしょう。たしかに経済的・時間的な自由はできるかもしれませんが、営業区域に関しては決まりがあります。個人タクシーの運転手は営業する区域に住み、原則として自宅と営業所が同一でなくてはなりません。例えば、東京都の場合「多摩地区」に住んでおり、そこに営業所を構えた場合、「東京23区・三鷹市・武蔵野市(武三地区)」での営業は禁止されています。将来的に個人タクシーになりたいと考えている方は、この営業区域のことも加味して住居の場所も選んでいきましょう。
個人タクシーと法人タクシーの違い
個人タクシーは、個人事業主が運営するタクシー業の形態です。この形態では、タクシーの所有者と運転手が同じ人物であり、自分の車を使って利用者を目的地まで運ぶことが特徴です。個人タクシーの最大の利点は、業務の柔軟性が高いことです。運転手は自身のライフスタイルに合わせて働くことができます。また、全ての収益が運転手自身に入るため、成功すれば収益も大きくなりますが、一方でリスクも個人が負担する必要があり、ビジネススキルや経営知識が求められます。
一方、法人タクシーは法人組織(株式会社や有限会社など)が運営する形態を指します。ここでは、タクシーの所有者(会社)と運転手が異なり、運転手は会社から給与を受け取ります。法人タクシーの利点には、所属する会社のリソースやノウハウを活用できること、安定した給与を得られることが挙げられます。ただし、運転手は拘束時間が長く、時間的な自由度が低いことや、売り上げの一部を会社に支払う必要がある(歩合給)といったデメリットも存在します。
要するに、個人タクシーは個人が自分の車を使ってタクシー業を営む形態で、柔軟性が高いがリスクも大きい。一方、法人タクシーは会社が運営し、給与が安定しても拘束時間が長く自由度が低いという特徴があります。
| 個人タクシーと法人タクシーの違い | ||
|---|---|---|
| 個人タクシー | 法人タクシー | |
| 免許・経験 | ・第二種免許取得 ・タクシー運転者等の経験10年以上 (申請者が35歳未満の場合は同一タクシー会社に限る) ・法令地理試験に合格すること | 第二種免許を取得していれば可 |
| 地理 | ・申請する 営業区域での経験が申請前に継続して3年以上であること (申請者が35歳以上40歳未満の場合) ・法令地理試験に合格すること | 東京、神奈川、大阪など一部の地域では地理試験に合格すること |
| 安全 | ・申請前3年間無事故無違反 (申請者が35歳未満の場合は10年間無事故無違反) ・指定された条件の任意保険に強制加入 | 特になし |
| 資金 | ・160万円以上 ※関東の場合 | 特になし |
| 設備 | ・車庫、整備などすべて自己負担 | 全て会社負担 |
| 住居 | 住居(自宅)と営業所が同一であること | 特になし |
| 定年 | 平成14年2月参入以降は、期限付き(75歳) (平成14年1月以前参入者は、条件付で期限なし) | 法人の規定による |
| 住居 | 住居(自宅)と営業所が同一であること | 特になし |
| 車両 | 専用車両(一人一車制) | 一台を社員複数名で使用 |
個人タクシーと法人タクシーの見た目の違い
ここまで制度的な違い、運転手になるための条件の違いについて紹介してきましたが、個人タクシーは見た目に関しても法人タクシーとは異なります。見た目に関しては大きく2つの違いがあります。
1つは、ボディーに書かれている文字です。個人タクシーには、車体側面ドア付近に「(個人)」との表示があります。車体の色と文字の色によって、見えにくくなっているものもありますが、良く見ると表示を見つけることができるでしょう。
もう1つは、行灯(あんどん)です。タクシーのルーフ(車体の上部)に何か乗っているのを見たことはあるでしょう。注意して見ると「○○交通」のように会社名が分かるようになっています。そのため、会社によって行灯の色や表記、形は異なります。業界の人やタクシーが好きな人なら、行灯を見て法人タクシーか個人タクシーかはもちろんのこと、会社名を言い当てることは容易なことです。
個人タクシーの行灯にもいくつかの種類があります。例えば、全国個人タクシー連合会(略称:全個連)はでんでん虫グループと呼ばれており、かたつむりの形をした行灯です。また日本個人タクシー連合会(略称:日個連、NKR)はちょうちんグループと呼ばれ、ちょうちん型の行灯です。この全個連にも日個連にも属さない個人タクシーも存在し、かまぼこ型や流れ星型の行灯も存在します。
個人タクシーの優良ドライバーのみが付けられるマスターズマーク
一部の個人タクシーには、三ツ星の行灯を装備しているものがあります。これはマスターズマークと呼ばれ、1998年に制定された優良個人タクシー事業者認定制度に合格したタクシーにのみ取り付けが許されています。
このマスターズマークを取得するには、一ツ星、二ツ星の認定を受けた上で、さらに申請を出し、マスター認定委員会の厳しい審査を受けなければ認定されないという、かなりハードルの高いものとなっています。運転スキルのみならず、接客スキルにも秀でた個人タクシー運転手であることを証明する
マスターズマークは、個人タクシー運転手なら誰もが欲する称号と言えるでしょう。
関連記事 タクシー運転手になるにはどんな資格が必要?ドライバーの条件とは
関連記事 プロドライバーになるための定義・条件とは
個人タクシー運転手の4つのメリット
メリット1:営業で得たお金をすべて自分がもらえる
タクシー会社に勤める法人タクシーの運転手の場合、給料の制度として歩合給を採用されていることがほとんどです。売り上げに対して歩率の分だけ、給料にプラスされるという仕組みです。歩率の高い会社でも65%ほどとなり、歩合以外の部分、この場合で言うと残りの35%はタクシー会社の収益となります。一方、個人タクシーの場合には、売り上げた金額すべてを自分がもらえる100%完全歩合給となります。自分の営業力次第で、効率良く稼いでいくことができるでしょう。
メリット2:時間的な拘束がない
個人タクシーは自営業となりますので、時間的な拘束がないというメリットがあります。もちろん働いて稼がなければ給料が減ってしまいますが、時間に融通が利くのはメリットでしょう。家族が急に体調不良になったときなど急用にも対応できますし、時間を自分で決められるため、介護などをしながら働くこともできるでしょう。時間に決まりがないため、割増運賃で料金の高くなる早朝・深夜だけ働くことや、昼間だけ働くことも可能です。
また、法人タクシーの場合には出社して担当となる車両の整備や準備、点呼、出庫点検などが必要になります。個人タクシーでも整備や点検は必要ですが、出勤や点呼などにかかる時間を削減できるメリットがあります。例えば、法人タクシーでこの通勤時間や点呼の時間が毎日2時間程度かかり、タクシードライバーの一般的な隔日勤務で月12日乗務すると、年間で288時間にもなります。この時間を個人タクシーの場合に乗務に充てたらと考えると、時間的な拘束がないのは大きなメリットと言えるでしょう。
関連記事 タクシードライバーの勤務形態・勤務時間を勤務スタイルの例で徹底解説!
メリット3:好きな車両で仕事ができる
法人タクシーの場合には、どの車に乗るかはタクシー会社が決めます。しかし、個人タクシーの場合には自分で車両を準備するため、好きな車両に乗れるというメリットがあります。車種やグレードを自分で選び、好みの車でタクシーの営業ができます。車が好きな方は特に、自分の好みの車両で仕事ができるのは嬉しいことでしょう。
メリット4:定年が75歳になる
タクシー会社の規定として定年が決められており、法人タクシーとして働く場合には基本的に60歳~65歳で退職となります。健康状態などによっては定年を超えても働かせてくれることもありますが、必ず運転させてもらえるとは限りません。しかし、個人タクシーの場合には定年は75歳となります。長く働きたいと考えている方には魅力的なメリットです。
個人タクシー運転手の4つのデメリット
デメリット1:車両の設備にかかる費用は自分が負担する
タクシー営業に使う車両を購入する費用や、ガソリン・税金・車検・整備など維持にかかる費用は自分で負担することになります。売り上げの費用はすべてもらえますが、初期費用やメンテナンス費がかかることは念頭に置いておきましょう。個人タクシーは自営業ですので、開業するにあたっては、それ相当の資金も必要になります。目安として設備資金に80万円以上、運転資金に80万円以上、その他車庫代や車の保険代などがかかり、200万円程度が必要になります。
デメリット2:ケガや病気で体調不良になったら収入を得られない
売り上げはすべて自分のものになりますが、自分が売り上げを得られなかった場合には、収入が得られないというデメリットがあります。法人タクシーであれば、売り上げが少なくても基本給として支給されますが、個人タクシーの場合にはそうはいきません。また、ケガや病気で出勤できなくなったときも法人タクシーの運転手には基本給があり、有給休暇を活用することも可能です。
デメリット3:事故やトラブルの対応が必要となる
タクシー営業をしていると、事故を起こしてしまったり、事故に巻き込まれてしまったりすることもあります。タクシー会社によっては事故・トラブルの対応をしてくれます。一方、個人タクシーの場合には事故やトラブルが起こっても自分で対応することになるデメリットがあります。
関連記事 タクシードライバーのクレーム対策・対応について
関連記事 タクシーで起きるトラブルとは?また対処方法は?
デメリット4:営業活動以外に確定申告などの申請が必要となる
タクシーを走らせ、お客様を乗せる営業活動が基本的な仕事となり、法人タクシーの場合にはタクシーの営業だけを行っています。しかし、個人タクシーの場合には営業活動以外に確定申告などの申請が必要となることには注意が必要でしょう。
個人タクシーの平均年収
個人タクシーの平均年収は約340万円程度ですが、これはあくまで全国平均であり都市部と地方では収入の格差が存在します。特に都市部ではタクシーの需要が高く、乗客数が多いため収入が高くなります。一方、地方では需要が限られるため収入は相対的に低くなる傾向があり、収入が最も高い地域と低い地域とでは年収に200万円を超える差がでています。
しかし以下のような効率的に稼ぐポイントを押さえれば、個人タクシードライバーの年収を向上させることが可能です。
・空車率の低減
空車率を低く抑え、需要の高いエリアや時間帯に的確に移動し空車時間を減らしましょう。
・高単価エリアでの営業活動
高単価エリアでの乗務を積極的に行うことで、収入を増やすことができます。タクシーの利用頻度が高い場所や、深夜帯に長距離利用される場所を把握して需要が高まるエリアに注力しましょう。
・顧客の利便性向上
顧客がタクシーを利用しやすい環境を提供することも重要です。クレジットカード決済やアプリを活用した予約システムなど便利なサービスを提供することで需要を増やすことができます。
・定期契約の獲得
定期契約を獲得することで、安定した収入を確保することができます。企業や施設との連携を図り定期的な輸送ニーズを担当することを目指しましょう。
以上のように効率的に稼ぐポイントを押さえれば、年収1000万円も夢ではありません。
個人タクシーの開業資金の目安
個人タクシーの開業資金の目安は、一般的に300万円から500万円程度といわれています。ただし、新車を用意する場合は開業資金が高くなる傾向があります。また、タクシー業務には特別な保険が必要であるため保険料の支払いや免許関連の費用も開業資金に含める必要がありますし、さらに開業時には集客や顧客獲得のためにタクシーの宣伝や広告費用も考慮する必要があります。その他ガソリン代や車両のメンテナンス費用、税金や手数料など日常的な経費も開業資金に含めるとよいでしょう。
開業するにあたっては、事前にどの程度の資金が必要になるのかを把握し、適切な計画を立てることが重要です。また、金融機関からの融資や補助金制度を調べて活用することもおすすめします。
個人タクシーの運転手になるための方法と手順とは?
個人タクシーの運転手になるための3つの方法・手段
個人タクシーの運転手になるには以下3つのいずれかが必要になります。
- 新規に許可を得る(新規許可)
- 既存の個人タクシー事業者から事業を譲り受ける(譲渡譲受)
- 既存の個人タクシー事業者の事業を相続する(相続)
それぞれ審査基準と年齢や運転経歴、法令遵守状況、資金計画などの諸々の条件をクリアしてはじめて申請、試験を受けることができるのです。
個人タクシーの運転手になるまでの手順
ここまで、個人タクシードライバーになる条件やメリット・デメリットについてお話してきましたが、そもそも個人タクシーの運転手になるにはどうやったらなれるのか、大まかな流れを簡単にご説明します。
- 地方運輸局に申請する
- 法令・地理試験を受験する
- 試験に合格し許可証を受け取る
- 事業所開始届を提出する
個人タクシーの申請は、営業区域ごとに地方運輸局で行います。申請時期や試験日などは、各地域の管轄ごとに違いますので、申請の際事前に確認しておくようにしましょう。これは、新規で申請する場合も譲渡の場合も同様です。申請が終わると、次は試験です。法令・地理試験に受験する必要があります。また、年齢制限や運転資金、運転経歴などの諸々の条件がちゃんとクリアできているかどうかをこの時点で判断されます。
すべて合格だった場合に許可書が発行されます。その後、事業所開始届を提出すれば、晴れて個人タクシー事業を開始できる流れとなっています。営業が開始できるまでの期間は、例えば11月実施の試験で合格した場合は、2月頃です。
個人タクシーの試験内容
個人タクシーの開業にあたっては、法令試験と地理試験の両方に合格する必要があります。
以下に試験内容と地理試験の免除条件についてご紹介します。
・法令試験
法令試験は、タクシー業務に関連する法律や規則に関する知識を問われる試験です。一般的に、45問中41問以上正解する必要があります。解答方式は語群選択式や〇×式が一般的です。
・地理試験
地理試験は、開業申請する区域の道路や交差点の名称、建造物、駅などの知識を問われる試験です。目的地まで向かう際の最短ルートやそのルートの走行距離・所要時間・運賃などについても出題されます。一般的に、30問中27問以上正解する必要があります。解答方式は語群選択式や〇×式が一般的です。
なお、開業申請区域にてタクシー・ハイヤー会社に乗務員としてのみ10年以上継続勤務し、かつ過去5年間無事故無違反である方と、開業申請区域のタクシー・ハイヤー会社に乗務員としてのみ15年以上継続勤務し、過去3年間の無事故無違反である方は地理試験の免除が認められることがあります。免除条件の詳細については、各都道府県や地域のタクシー協会や運輸局のウェブサイトで確認することをおすすめします。
【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」のうち地理試験の廃止が決定しました。詳細は各協会または組合へご確認ください。
開業を支援してくれるタクシー会社
個人タクシーを開業したいエリアが決まっている場合、そのエリアにあるタクシー会社に所属することが効率的です。既存の会社に加入することで、すでに確立された営業エリアでの運行をスムーズに始めることができます。また、一部のタクシー会社は、個人タクシーの開業を積極的に支援・サポートしています。営業区域の規定には注意が必要ですが、このような会社に所属することで、開業に関するアドバイスやサポートを受けることができます。制度を活用することで、スムーズな開業が可能です。
【開業支援をしているタクシー会社】
日本交通株式会社
国際自動車株式会社
二重交通株式会社
日本交通株式会社
日本交通は、タクシードライバー向けの新たなキャリアパスとして、個人タクシー事業者との業務提携をスタートしました。この提携の最大の利点は、個人事業主として独立した後も「日本交通のブランドで営業を続けることができる」という点です。日本交通の個人タクシーキャリアパスには、「無線配車」「日本交通専用乗り場」「四社タクシーチケット」「アプリ配車」といった、日本交通のサービス基盤を活用する機会が提供されます。
この提携において、運行管理規定などは原則として、日本交通と同じものが適用されます。つまり、これまでの日本交通で培ったタクシードライバーの経験やノウハウをそのまま活かしながら、個人タクシーの業務を遂行できるのです。
国際自動車交通株式会社
km提携個人タクシー制度は、国際自動車が2016年4月15日に導入したタクシードライバー向けのキャリアパス制度です。この制度は、個人タクシー事業の開業前後において支援を提供し、開業後は業務提携会社として、引き続きkmグループの一員として活動することができる仕組みです。個人タクシードライバーは国際自動車との業務提携を通じて、決済手段や端末、国際自動車の特別なサービスや車両装備、そして福利厚生などを共有できます。国際自動車から提供される充実したサポートにより、個人タクシーの開業がスムーズに行える点が、この制度の最大の利点です。つまり、この制度を利用することで、個人タクシードライバーは独立事業者としての自立性を保ちつつ、国際自動車のサポートとリソースを享受することが可能となります。
二重交通株式会社
ふたえ交通は個人タクシーを目指すドライバーさんを応援。年に2~3人程、個人タクシーのドライバーを輩出してています。個人事業主として独立した後も専用乗り場や無線配車、アプリ配車の利用相談が可能です。
個人タクシーになったら組合に入ろう
個人タクシーの組合に入ると様々なサポートを受けることができます。組合には、「東京都個人タクシー協同組合」と「日個連東京都営業協同組合」があり、加入には月に5万円ほどの費用はかかりますが、個人タクシーの運転手はこの組合に入っている方も少なくありません。
■組合から受けられるサポートの種類
- 個人タクシー免許を取得するための講義等
- 開業に必要な事業譲渡の紹介等
- 車両購入にかかる資金の貸し付け
- 無線配車
- 申告書類などの作成支援
- 定期健康診断の補助
- タクシーチケットやクレジット支払いなどの未集金の換金
関連記事 タクシー運転手になるにはどんな資格が必要?ドライバーの条件とは
個人タクシーも配車アプリが利用可能
個人タクシーも「GO」や「S.RIDE」というタクシー配車アプリが利用可能です。法人タクシー業界では最近、配車アプリの競争が激しくなっていますが、個人タクシーにも実はスマートフォンの配車アプリが存在します。
タクシー配車アプリ業界のリーダーである「GO」や「S.RIDE」は、日個連東京都営業協同組合や東京都個人タクシー協同組合と提携して、利用できるようになっています。また、西日本個人タクシー共同組合でも「GO」の利用が可能です。ただし、地域によって利用できるかどうかが異なり、すべての組合の車両が対応しているわけではないので、利用可能かどうかを確認する必要があります。
まとめ
自由に働くことのできる個人タクシー。時間に縛られないのは魅力的と言えるでしょう。ただし、個人だからこそトラブルの対応を自分1人でしなくてはならないなどのデメリットもあります。ここに紹介したメリットとデメリットを参考にして個人タクシー運転手を目指すかどうか考えてみてはいかがでしょうか。もし個人タクシー運転手になろうと思った場合には、タクシー会社で10年乗務をする必要があります。今個人タクシーにはなりたくないと思っていても、数年経って個人タクシーになりたくなるかもしれません。その可能性も考慮すると、少しでもタクシー運転手に興味があるのなら、すぐにでも始めるべきと言えるでしょう。
タクシー運転手は40代、50代以上などの中高年の方でも未経験から活躍できるチャンスがありますので、ご転職をお考えの際はぜひタクシー業界も検討してみてください。これからタクシーの仕事をお探しならドライバーズワークでタクシードライバー・運転手の求人を検索していきましょう。タクシー業界に精通したキャリアアドバイザーが相談に乗ることも可能!お悩みの方はぜひ活用してみてください。
ドライバーズワークの公式ウェブサイトであるタクノート -タクnote- では、タクシーに関連する様々なコラムを豊富に取り揃え、タクシードライバーとしての知識やスキル、業界の最新トレンドなど貴重な情報を提供しています。ぜひタクノートを利用して、あなたのタクシードライバーとしてのスキルや知識を向上させましょう!
休日が多めの求人
休日が多めの求人一覧はこちら
タクシードライバーへの転職で失敗しないために
タクシードライバーの求人をお探しならドライバーズワークにご登録・ご相談ください!ドライバーズワークは東京・神奈川・愛知・大阪などの関東・東海・関西エリアを中心としたタクシードライバー(運転手・乗務員)求人サイトおよび転職支援サービスです。タクシー業界に特化した詳しい求人情報が満載!ご登録はかんたん1分無料!タクシー業界の知識量も豊富な、専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの担当に付き、転職にまつわるあなたのお悩みにお答えするだけでなく、転職をするべきなのかどうか、転職をする場合にどういった基準で会社選びをすれば良いか、などを一緒に考え丁寧にお伝えします。まだ転職するかどうかを迷っている段階の方も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
関連記事
知識の人気記事
よく読まれている記事
- 知識
タクシー運転手になるにはどんな資格が必要?ドライバーの条件とは
【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...
- 知識
【地理試験の疑問】過去問・テキストの入手方法や受験場所・時期!タクシードライバーになるには必要?
【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...
- 知識
タクシードライバーの勤務体系・勤務時間を勤務スタイルの例で徹底解説!
みなさんが普段見かけるタクシーは朝も夕方も夜中も走っており、いつ休んでいるのかと思うほどどの時間帯で見かける...
- 知識
タクシーの営業区域や区域外営業などエリアについて
タクシーは場所を選ばず自由に営業をして良いという訳ではありません。「営業区域」と呼ばれる、タクシー会社ごとに...
- 知識
タクシーに自転車は乗せられる?自転車を積む方法と運ぶ際の注意点
趣味で自転車に良く乗る方や、自転車で通学・通勤をしている方にとって、途中で自転車に乗れなくなってしまった場合...
- 知識
タクシー車内で飲食しても良い?守るべきマナーも紹介
タクシーにまつわるマナーの1つに、タクシーの車内で飲食することの是非があります。今回はタクシー車内での飲食に...
タクシードライバーについて知る
他のコラム内カテゴリもチェック!
キャリア
タクシードライバーとして仕事をするにあたってのお役立ち情報をご紹介します。タクシーエンタメ
タクシー業界に関連する面白いエピソードや、エンターテイメント情報をご紹介します!タクシーニュース
タクシー業界や運輸業界に関する新着ニュースをご紹介!タクシーの種類
利用シーンによって様々あるタクシーのサービス形態をご紹介します!テクニック
タクシードライバー(運転手)としてのテクニックにまつわる情報をお届け!無線グループ
大手グループから地域密着のグループまで!無線グループの特徴をご紹介します。Q&A
タクシー業界やタクシードライバーに関するよくある質問にお答えします!知識
タクシー業界にまつわるトリビアや豆知識情報をご紹介します!





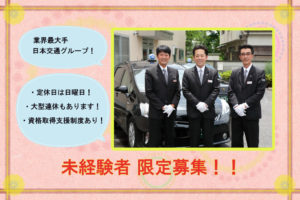









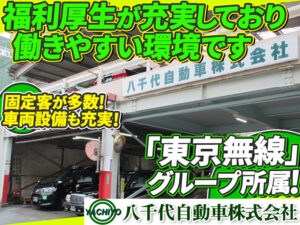
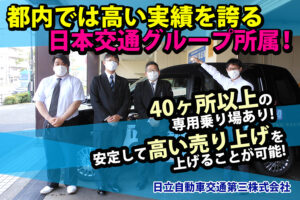



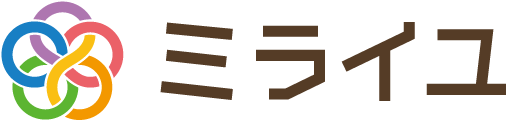














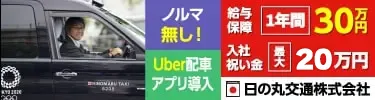




 無料会員登録
無料会員登録 